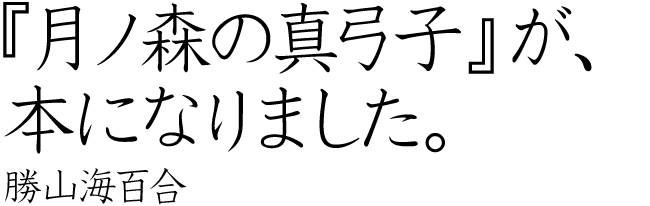
マトグロッソにて連載していた勝山海百合さんの『月ノ森の真弓子』、
勝山さんにとって初の日本、それも出身地・東北を舞台に紡いだ
幻想奇譚が、今回ついに書籍になりました。
加筆もたっぷりして頂いて… 6月15日発売!

ここは、癒しの森。
岩手と宮城の狭間に秘かに存在する「月ノ森」。この地で湧水「命迦泉」の番を始めた駿矢と姪の真弓子は、様々なものと巡り逢う。人と、人にあらざる者と……。
中国をはじめアジア各地の神仙、怪異譚や幽霊話を得意としてきた著者が初めて描いた東北の物語にして、幻想奇譚の書き手としての実力を如何なく発揮した意欲作です!
[目次]
第1 話 山帰来
第2 話 月ノ森
第3 話 命迦泉と山の神様
第4 話 金華チェリー
第5 話 真弓子、学校に行く
第6 話 海とぼた餅
第7 話 夢箱
第8 話 巫女と魔女
第9 話 ハロー、グッバイ、ハロー
第10話 幻の仙人カレー
第11話 ハルとサク
第12話 山の教室
第13話 汗をかく馬
第14話 山荘の夜
第15話 月ノ森の姉サ
*エピローグ
[おためし読み]
第1章 山帰来
北本州と旧房総半島のあいだに架かる秋津大橋の完成はまだ先で、東京ベイ・フェリーの船上からは見えるようで見えず、見えたとしてもそのシルエットは心許ないもののはずだ。東京湾の、陸地に近い浅いところを通ると、海面から突き出る遺跡が見えた。ビル群、首都高速道、観覧車。東京の低い土地のあらかたが水に沈んだ直後、東京湾は汚染海水でいっぱいだったが、重油を分解するバクテリアや藻類(そうるい)などの導入と知恵と十数年の時間をかけて、観光資源になるところまで回復していた。
船室のドアから、十歳ほどの、灰色のパーカーに膝丈のズボンの子どもが甲板に現れた。短い髪を潮風が撫でる。くっきりとした二重の目が輝き、元気な男の子に見えた。
子どもは、「すごい!」と声を上げていたかと思うと、しゃがみ込み、手すりの柵のあいだから海面を覗き込み始めた。やがて静かになった。
三十歳にはまだ届かないくらいの男が、どうした? と声を掛ける。男は白いボタンダウンのシャツにポケットの多い焦げ茶色のベストを着ていたが、シャツは洗いざらしで袖口が擦り切れていた。子どもは青ざめて、ついさっきまで輝かせていた目をぎゅっと閉じていた。船に酔ったらしい。
「だから近くを見るなと言っただろう」
「ぎぼぢ……」
気持ち悪いと言い終わるまえに、子どもは、喉の奥からごごっという音をさせて、胃の中のものを海面に吐き出した。パーカー、青いTシャツの下のか細い体が上下した。男は片手で子どもの腕を掴み、片手で背中をさすった。胃の中が空になると、子どもをベンチに座らせ、遠くを見てろと言い残して船内に姿を消した。
船のそばを海鳥が飛び交う。船とイルカが併泳するのを見るのを楽しみにしていた子どもは、青ざめたまま目を潤ませていた。
「ほら、あれ、見たかっただろ」
戻って来た男が励ましの声を掛ける。誰かのはしゃいだ声がした。東京が日本の首都だったころに建った巨大な電波塔が、かつて首都があった記念碑のように海面からのぞいており、それを見るのも子どもの楽しみの一つだった。子どもは、一瞬目を開け、「ラ・トゥール(塔)……」と呟いて、また吐いた。
男は子どもに買ってきた水を飲ませたが、水が喉を通る刺激に反応したのか、すぐにまた子どもは船縁に駆け寄って飲んだ水を吐いた。
「よかったら、これどうぞ」
白いウィンドブレーカーを着た、二十四、五歳に見える女が、頬にかかる髪を片手で押さえながら、ガラスの小瓶を差し出した。てのひらの中にすっぽりと隠れそうな大きさで、白い花のラベルが貼られている。男には見慣れなかったが、市販されているものらしかった。これは? と女に聞いた。
「船酔いにも効く万能オイル。頭痛、切り傷、虫刺され、なんにでも効くんです」
女の声を聞きながら、男が瓶の蓋を開け、手であおいで匂いを嗅ぐと、精油らしい刺激臭を感じた。ラベルには漢字が並ぶが、日本語ではなかった。
「船酔いのときは、手首の、ここのところに塗りこむんです……ほんとうなら、酔うまえに」
女が自分の手首の内側、親指の付け根の下のあたりを人差し指の先で触って見せた。
男は瓶から薄い緑色のオイルを二、三滴指先に垂らすと、子どもの両手首の内側を親指の腹で擦った。鼻にすっと抜ける香りが良かったのか、子どもがくすぐったがって笑い、身をよじった。
「冬青(そよご)、ユーカリ、薄荷(はっか)、樟脳(しょうのう)……なんかが入っているらしいんですけど、馴染んでいるせいか、匂いを嗅いだだけで安心してしまうんです、わたし」
「この匂いが、効くのかもしれませんね」
子どもは男の腕の中で、おとなしくしていた。
「息子さん? 弟さん?」
女が聞いた。男はちょっと笑って見せた。
「強いて言えば保護者、かな」
男は女に瓶を返そうとした。
「よかったら、使って下さい。また役に立つかも知れないので。わたしの分は、予備がありますから」
男は花のラベルの小瓶をありがたく譲られた。
「あの……」ためらいがちに女が言った。「ボタン、とれそうです」
女に指摘され、男は自分の胸に目をやり、シャツの三番目のボタンが弱くなった一本の糸で辛うじて繋がっているのを発見した。
「あ、どうも」
言うなり、男はボタンを引きちぎった。あとでつけ直そうと思ったのだ。
「差し出がましいようですが、便利なものを持っていますので」
女が肩に掛けたバッグからポーチを出し、そこからステープラーの針のようなものを取り出して見せた。
「貸して下さい」
そう言って男からボタンを受け取ると、ボタンの二つの穴に針を通し、そのままシャツに刺した。針の先をねじって倒し、抜けないように留める。
「応急処置です」
「すみません。いえ、ありがとうございます」
男が礼を言うと、女は照れたように頭を下げ、そのまま顔も上げずに男から離れていった。
習志野港から連絡バスで新松戸駅、そこから武蔵野線で新大宮駅に行き、新青森駅行きの東北新幹線に乗車した。子どもは体ほどの大きさの黄色いバックパックを背負って、よそ見をしながら男の後ろをついてきた。予約の指定席に来ると、男は荷物を頭上の棚にのせ、子どもを窓際に座らせた。
ゆったりとした短いメロディがホームに流れ終わると、車窓の景色が動き出し、乗客に振動を感じさせないほど静かに発車した。
乗ったばかりのうちは車窓に張り付いていた子どもだが、車内販売のアイスクリームを食べ終えると、座席に身を預けて寝息を立て始めた。そのまま深い眠りに落ち、くりはら高原駅で「降りるよ」と男が掛けた声も、しばらく耳に届いていないようであった。それでも意識を取り戻すと、まるで眠ってなどいなかったかのように元気よく立ち上がり、「あっという間でつまんない」と呟きながらバックパックを背負った。
本陣前と表示されたバスの停留所の標識は、赤で記されたバス会社名も黒で記された地名も文字が薄れていた。
バスを降りると、空気に水と植物の匂いが満ちているのがわかる。遠くには山が、手前には水が張られ、若い稲が植えられた水田が並び、山と水田のあいだには森があった。バスが行ってしまうと、ひび割れたアスファルトの道には車も人影もない。
「なんにもない……」
不安げに子どもが呟いた。
「田んぼと畑と、家はある」
「家?」
男が、ほらと目で示した先に、生け垣に囲まれたトタン葺きの屋根が見えた。太陽光発電のパネルが光っている。そこを目指して、二人は歩き出した。水に浸かった幼い稲の葉が風に揺れて、さざなみを生み出していた。
田んぼのあぜ道を歩いて、槙(まき)の生け垣の中に入った。母屋の前は広く空いており、花壇があった。納屋には自動車が二台、一台は軽トラックで、もう一台は乗用車だった。
「ここが我々普賢堂(ふげんどう)家の分家だ。まあ、本家はもうないけど」
「ブンケ?」
納屋に繋がれた犬が一声吠えた。クリーム色の被毛で、耳や鼻先が黒い、中型の日本犬だった。子どもがびくりとして、「うわわ」と言った。
「池月(いけづき)、静かに」
花壇から声がしたかと思うと、ボンネットタイプの日除け帽子を被った中年の女性が立ち上がった。手にはむしった雑草が掴まれていた。それから男のほうに目をやると、「駿矢【しゅんや】くん」と呟き、電話をくれたら駅に迎えに行ったのにと呆れたように言った。
男が、「これからさんざんお世話になるので、最初くらいは面倒を掛けないでおこうかと思って」と言うと、言い終わらないうちに「水くさい」と返された。
さっそく犬に挨拶をし、お返しに匂いを嗅がれても怯えもせずに背中を撫でている子どもに目をやると、女性は、嬉しそうに笑みを浮かべ、
「犬、好き?」
と聞いた。
「大好き。猫も、小鳥も」
「そう。これはうちの池月」
池月と呼ばれた犬が、盛んに尾を振った。
「いけづき?」
名付けの理由に興味が湧いたのか、子どもが好奇心いっぱいの顔を上げる。
「昔の名馬の名前よ。疲れたでしょう、さ、お上がんなさい」
と言って二人を玄関に導くと、女性は土のついた靴を脱ぐために、勝手口に回った。
「馬の名前なんだ……知ってる?」
子どもが男のほうを見ると、「さあ?」と肩をすくめた。
女性の姿が見えなくなると、子どもは小声で、「ここのうちの子どもになるの?」と聞いた。それがいかにも不安げだったので、男はからかいたくなったが、それは堪えて、
「良い子にしているんだぞ」
とだけ言って、お邪魔しますと靴を脱いで上がった。
「そこで休んでー」
と女性の声がしたので、玄関を上がったすぐ脇の部屋に入った。畳の間に花と唐草模様が織り出されたシルクの絨毯が敷かれ、ソファとテーブルが置かれた居間になっていた。すすめられて二人は並んでソファに腰を下ろした。
帽子を脱いだ女性が顔を出した。額や目尻にはくっきりと皺が刻まれていたが、血色の良い頬には艶があった。
「お茶でいい? コーラもあるけど?」
と女性に聞かれて、男はルートビアと答えた。女性は、
「黒松沙士(ヘイソンサーシ)しかないけど、いい?」
と聞き返した。悪戯っぽい目が笑っている。
「あるんだ」と男は笑い、「じゃあ、それで」と言った。
「あなたもサーシ?」
尋ねられて子どもは激しく首を振った。サーシが何かはわからないが、薬品のような味がするルートビアは苦手なので、同じようなものだと察したのだった。
「麦茶にしましょうね」
「……お願いします」
ほどなく、“台湾のルートビア”と言われる黒松沙士の缶とグラスに入った麦茶が二つ運ばれてきて、二人の前にコースターと飲み物がそれぞれ置かれた。大ぶりの胡桃ボタンに似たマコロンが入った菓子鉢も蓋をとって置かれた。
女性も二人に斜めに向き合う場所に腰を下ろした。
「いただきます」
子どもが手を合わせる。
「はい、どうぞ」
それに女性も答えた。
落花生の粉が練りこまれた焼き菓子にさっそく手を伸ばす子どもを二人で見ていたが、やがて思い出したように、男が居住まいを正し、
「和香菜姉さん、このたびは、お世話になります」
と頭を下げた。子どもも、両手を膝の上に置いて、慌てて頭を下げた。
「こちらこそ、駿矢さんに無理を言って、ごめんなさいね」
「いえ、かまいません。むしろ渡りに船で。子連れになっちゃって」
「子どもは歓迎、気持ちだけでも若返るし」
女性が笑うと、白粉気のない目尻に鳥の足跡のような皺が寄った。
「私はこの家の普賢堂和香菜。真弓子(まゆみこ)ちゃん、よろしくね。仲良くしましょう」
「真弓子です、ふつつか者ですが、よろしくお願いします」
神妙な顔で言うので、和香菜は思わず笑って駿矢に目を向けた。
「ふつつか者とか、あなたが教えたの?」
「勝手に覚えるんですよ」
駿矢が困ったように言いながら、黒松沙士の缶に手を掛けてプルトップを起こすと、缶から茶色い泡がぶくぶくとあふれ出した。
「あ、冷えてないから、吹き出すかも」
和香菜が駿矢に布巾を手渡した。
「先に言って下さいよー」
こぼれた飲み物を拭きながら軽く抗議をすると、真弓子が声を上げて笑い出した。鳴子(なるこ)が強い風に揺れるような、リズミカルな笑い声で、ワライカワセミの警戒音を耳触り良くしたようだった。
真弓子は体をよじって笑い、発作のようにひとしきり笑うと、
「叔父さん、ちょろい」
と目に涙を滲ませたまま、切れ切れの息で言った。
「真弓子ちゃんは笑いんぼさんね」
和香菜が言うと、真弓子はソファに体を倒したまま、「笑ったの、久し振り」と呟いた。駿矢も久し振りに聞く真弓子の笑い声だった。
「お腹痛いくらい、笑っちゃった」
体を起こした真弓子は、恥ずかしそうに呟き、麦茶をごくごくと飲んだ。それから、マコロンに手を伸ばして一つをとり、口にした。さくさくという咀嚼音のあと、「美味しい!」と呟いた。
「あら、お口に合うなんて光栄ね」
「クッキーみたいなんだけど、ちょっと違う味」
「ご明察。ピーナッツの粉が入っているの」
真弓子は感心すると、二つ目に手を伸ばした。駿矢も、小学生のとき以来のマコロンを食べてみた。
子どものころに大きく感じたものも、大人になって改めて向き合うと記憶ほど大きくない、そんなことがしばしばあるが、マコロンは子どものころの味のまま、変わらなかった。ピーナッツの香りが香ばしく、懐かしい味だった。
「でもおやつはほどほどにしてね。夕飯が美味しくなくなるから」
三個目を食べていた真弓子は、四個目に手を伸ばしかけて、止めた。
今度は駿矢が笑った。和香菜の言い方が祖母や母親にそっくりだったからだ。和香菜はこの家、駿矢の祖父の生家であり、「分家」と呼ばれる家の長男の妻で、駿矢の母親とは血の繋がりはないのだが。分家のルーツである本家は絶えて久しかった。
「それから、裏の田んぼの向こうに、山があるでしょう? あっちのほう――」和香菜は、家の中から指をさした。
「森っていうか、雑木林みたいな。月ノ森。迷子になるから一人では入らないでね。先のことだけど、八月十六日だけは特に……」
真面目な顔で和香菜が言うので、真弓子も真剣に頷いた。頷いたものの、
「どうして?」
と尋ねた。和香菜は、
「お盆の終わりだからかな? ご先祖様があの世に帰るから、一緒に連れて行かれないように? まあ、そういう決まりなんだって。神様との約束なのかもしれない。私も、言われたことを守ってるだけだから……」
と困ったように言い、話題を変えた。駿矢は、夏の終わりの海水浴で、浮き輪に掴まって遊んでいるうちに、引き潮で思いがけず沖に運ばれて戸惑う子どもを想像した。
和香菜が尋ねた。
「お腹がすいているなら、夕飯は早めに始めましょうか?」
「そうしてもらえると、ありがたい。息子たちは?」
「長男は大学、次男はいま……ハワイ沖」
「え? じゃあいま、この家に和香菜さん一人?」
「そうなの。だから気楽にしてね」
一息ついたころ、和香菜は二人を八畳の床の間つきの和室に案内した。床の間には紫陽花の軸が掛かっていた。
「離れには明日案内するから、今日はここで休んでちょうだい」
「すみません」
駿矢は荷物を部屋の隅に置くと、さっそく畳の上に横になった。
「叔父さん、寝るの?」
真弓子が尋ねた。
「ちょっと横になるだけ」
「犬と遊びに行ってもいい?」
「遠くへ行くなよ」駿矢は自分の腕を瞼(まぶた)に乗せた。「車に気を付けろ。はねられるなよ」
「わかった。それからね、あたし、ここんちの子どもになら、なってもいいよ」
そう言うと、真弓子は襖を開けて、廊下に飛び出した。駿矢は真弓子の現金さに一人で笑った。
真弓子は、台所の和香菜に「池月と遊んでいい?」と声を掛けると、「え?」と聞き返した和香菜の声を承諾と捉えて、運動靴を履いて庭に飛び出した。
ンをはいた真弓子は、まるで男の子のようで、自分の息子たちが幼かったころを思い出した。
「あんまり遠くや、危ないところには行かないでね」
声を掛けたが、真弓子の耳に届いたかはわからなかった。
真弓子が田んぼのあぜを歩いていると、前のほうから同じくらいの年頃の男の子が歩いてきた。すれ違うまえから、池月が嬉しそうに尻尾を振った。真弓子が歩みを止めると、黙ってしゃがみ、犬の頭や首筋を撫でまわした。そして真弓子のほうは見ずに、
「池月のうちの人?」
と聞いた。
「……たぶん」
「引っ越してきたの?」
「うん」
「何年生?」
「五年」
「おれ、飛び級六年」
撫でられていた池月が、空のほうに顔を向けた。二人も反射的に空を見上げると、青い空に、白い雲が一筋、力強くたなびいていた。その形はまるで、没骨法(もっこつほう)で描かれた龍のようだった。
「すっげ」
「龍みたい」
池月が吠えると、男の子は我に返って斜めに掛けたスポーツバッグから携帯端末を取り出し、空に向けて付属のカメラのシャッターを切った。
「撮れた?」
真弓子がモニターを覗き込んだ。龍に見えた雲は、小さなモニターの中ではただの細長い白い線だった。
男の子は、ちょっと口元をゆがめると、「目で見たからいいや」と言った。
「散歩?」
真弓子は頷いた。
「おれも、ときどき池月の散歩するんだ。道順知ってるから、一緒に行ってやろうか」
真弓子が頷くと、男の子はいま来た道を振り返って、「こっち」と歩き出した。
あぜ道が尽きると雑木林の細い道に入っていった。木肌の赤い松に藤の蔓が絡み、蕾をいっぱいにつけた花房をいくつも提げていた。マメ科の花らしい、スイートピーのような甘い匂いがかすかにした。
道の先には小さな谷があり、木漏れ日が差し、水面がきらめいていた。
「おばさんが散歩させるときは、こっちは通らないんだけど」
そう言いながら、小川のせせらぎから突き出た灰色の岩を渡った。
池月も怖がらずに石を渡り出したので、真弓子もあとに続いた。
「すごく、きれい」
「こんなので、驚くなよ」
男の子が振り向きもせずに得意げに言った。
雑木林を出て、人が歩きやすそうな道に合流したかと思うと、男の子は道を渡り、斜面を駆け上った。藪の中をずんずん進んでいく。草の葉や、棘のある枝が肌を撫でた。緩い斜面を上りきったかと思うと、今度は下り坂になった。池月が怯えずに男の子のあとについていくので、真弓子もあとに従ったが追いつけず、うっかり手からリードが離れた。逸る気持ちを抑えながら慎重にしゃがみ腰を落としながら、転ばないように下りていった。運動靴の底が滑った。一足先に下まで降り立った男の子が、黙って立っていた。木々のあいだに苔むした巨石があり、そこから湧き出した水が小さな滝になって流れていた。
「……」
真弓子は呼吸も忘れて見上げ続けた。和香菜の家からもバス停からもそう遠くないはずなのに、深い森の奥のような場所があるとは驚きだった。
「ここには、湧き水の神様がいるんだ」
「すっごい」
「あそこ」
男の子が指を差す先には枝を伸ばした大木があった。枝に、明らかに別種の植物が根を張り、土筆のような節のある茎を伸ばしている。茎には楕円形の葉がついている。
「野生の蘭。デンドロビウム。もうすぐ白い花が咲く」
真弓子はデンドロビウムがどんな花か、すぐには思い浮かばなかった。蘭と言うので、豪華な大輪のカトレアを連想した。
「ここのことは秘密、内緒だぞ。学校に行っても、女子には言うなよ」
「なんで?」
真弓子が聞き返したので、男の子は意外そうに真弓子を見た。その瞬間、まさか女子か……?と胸中がざわめいたが、直接聞くのもためらわれたのか、男の子はそれ以上は口を開かず、
「暗くなるから、帰ろう」
それだけ言うと、木の枝を掴みながら斜面を上った。再び道に出る。
「こっちの道を下りていくと、おばさん家の前に出るから」
じゃあな、と言うと、男の子は坂道を駆け上り出した。池月が反射的に男の子を追いかけたので、真弓子は走っていって、リードの端を掴んだ。
「じゃあな」
男の子は振り返ると、ぶっきらぼうにもう一度言って、走り去っていった。
▼
▼
▼
この続きは書籍でお楽しみください!
▼
▼
▼
▼
▼
この続きは書籍でお楽しみください!
▼
▼
▼

|
『月ノ森の真弓子』 イースト・プレス刊/1500円+税 6月15日発売! 装画:小沢さかえ 装丁:アルビレオ 四六判 並製 288頁 |
2014/06/12 更新





